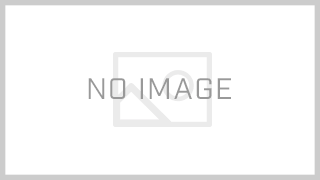太宰治『女生徒』と句読点
知人が、太宰治の『女生徒』がいいと言うので、文庫本を買って読んでいるが、どうにも句読点、正確には「、」(読点)が多すぎて、文体というか、リズムが馴染まない。
短編の他の作品では、これほど読点が多いわけではなく、この『女生徒』がすいぶんと特徴的で個人的に合わないような感覚がある。
たとえば、『女生徒』の冒頭は、こんな風に始まる。
あさ、眼をさますときの気持は、面白い。かくれんぼのとき、押入れの真っ暗い中に、じっと、しゃがんで隠れていて、突然、でこちゃんに、がらっと襖をあけられ、日の光がどっと来て、でこちゃんに、「見つけた!」と大声で言われて、まぶしさ、それから、へんな間の悪さ、それから、胸がどきどきして、着物のまえを合せたりして、ちょっと、てれくさく、押入れから出て来て、急にむかむか腹立たしく、あの感じ、いや、ちがう、あの感じでもない、なんだか、もっとやりきれない。
出典 : 太宰治『女生徒』
内容がどうと言うより、まずこのリズム、この呼吸に、その都度合わせることに苦労する。
この辺りは、ほんとうに相性なのだと思う。
句読点が多い文体自体というのは、太宰治なりの文学的な表現や狙いがあるのだと思う。
もともと読点による淡々とした短いリズムは、太宰の文体の特徴の一つだとは思うが、この『女生徒』は特に多い印象を受ける。
若い女性の頭のなかを表現しようとしたときに、このぶつ切りのリズム、というのが、合っていると感じたのか、あるいは、幼さの表現というのもあるのかもしれない。
幼い子は、「あのね、わたしね、きのうね、」と一つずつ区切って話すことがある。一続きにすうっと流れるように話すことができない。
その感覚も、もしかしたら太宰は表現したかったのかもしれない。